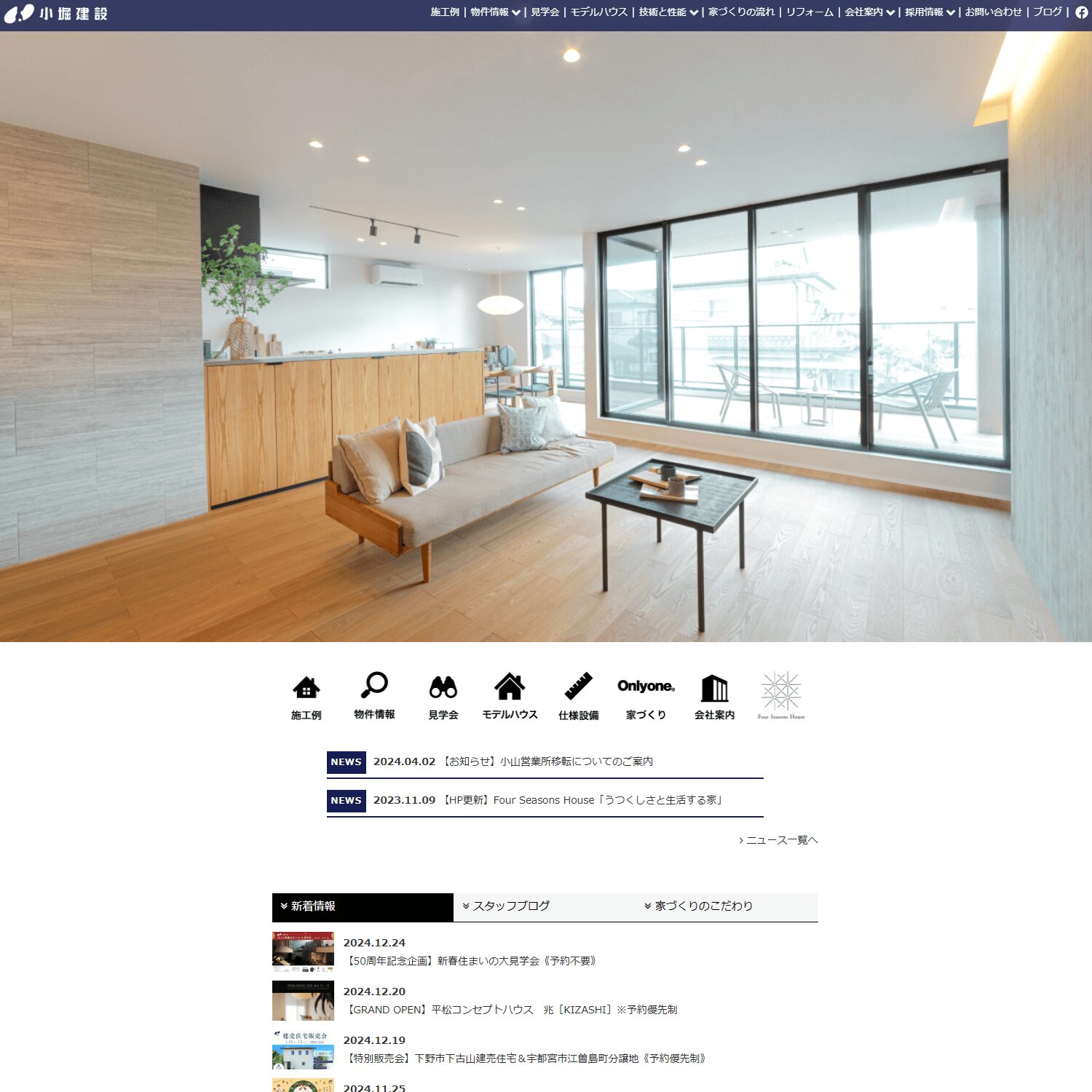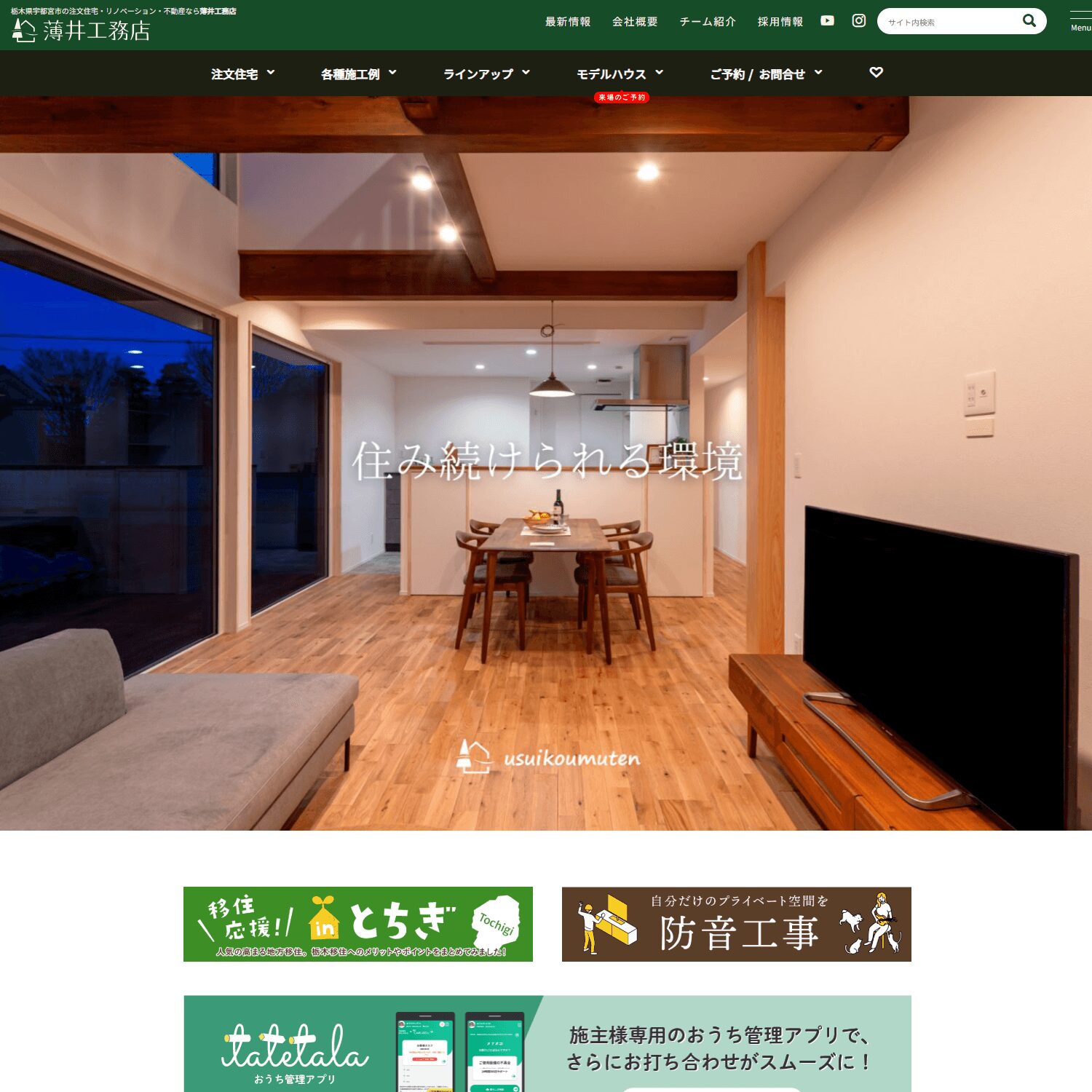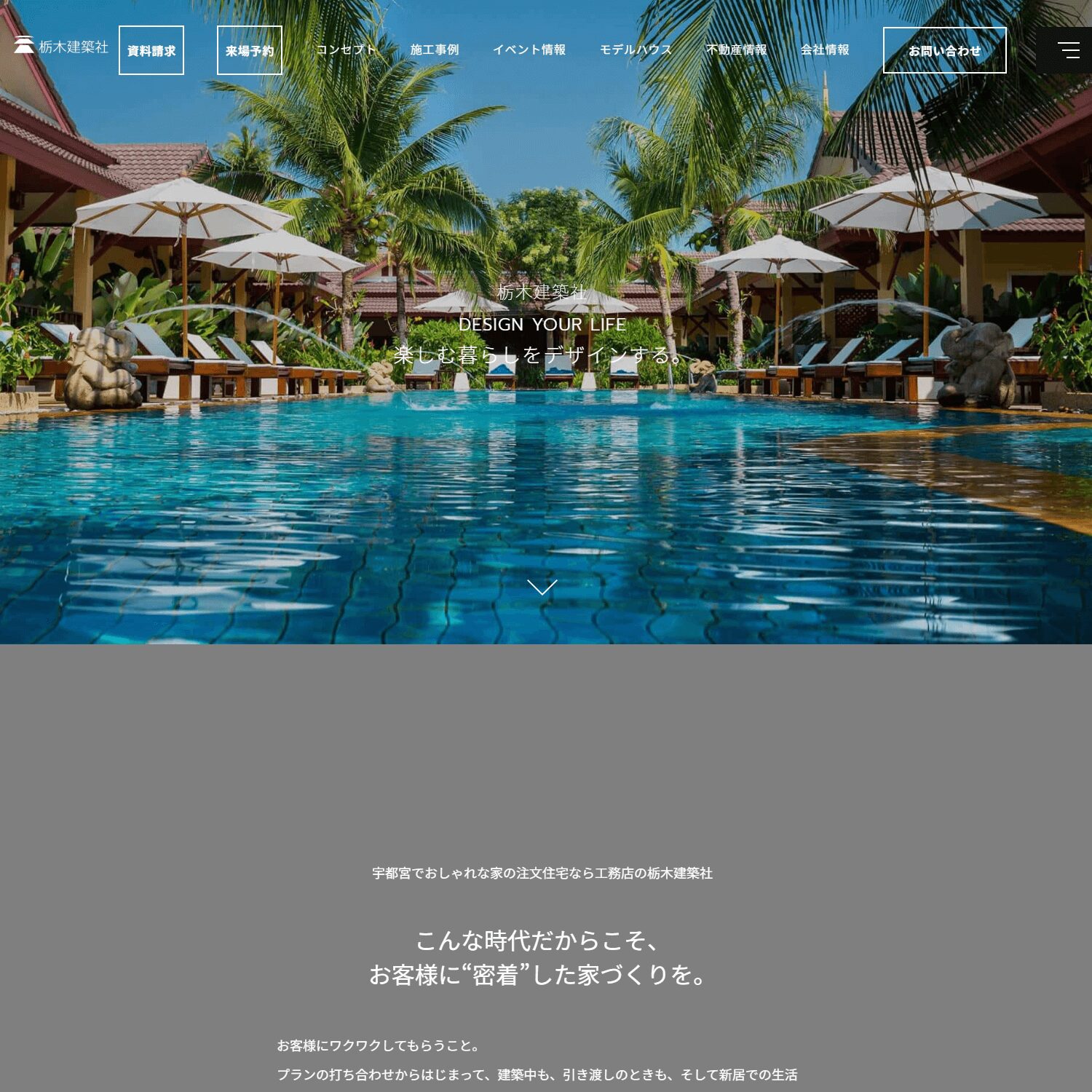長期優良住宅についてお伝えします。長期優良住宅という言葉をよく見かけるけど、実際どのような住まいを指すのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。長期優良住宅には、さまざまな優遇措置が設けられている一方で、注意点もあります。長期優良住宅の認定基準やメリット・デメリットについて、詳しく紹介します。
長期優良住宅の認定基準
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用できるよう、構造や設備に措置を講じている高性能な住宅を指します。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の長期優良住宅認定制度の基準をクリアし、国からの認定を受けた住まいです。申請する建築および維持保全に関する計画が、一定の基準を満たす場合に認定を受けることができます。
劣化対策
劣化対策等級(構造躯体等)等級3に該当することに加え、床下に一定以上の空間確保や点検口の設置が定められています。劣化対策では、数世代にわたり居住できる構造躯体であることが求められます。
耐震性
極めて稀に起こる地震に対する継続利用の改修の容易化を図り、対策を講じて損傷レベルを低減させます。住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に定める免震建築物であることや住宅構造に応じた耐震等級1~3(倒壊等防止)の取得などの措置を講じます。
省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能を確保することが求められます。断熱等性能等級「5等級」かつ一次エネルギー消費量「6等級」の基準に、適合することが必要です。
維持管理、更新の容易性
構造躯体と比較して、耐用年数が短い設備配管のメンテナンスについての基準です。点検や清掃、補修など、設備配管をメンテナンスしやすいように措置を講じます。新築戸建て住宅の基準は、維持管理対策等級(専用配管)「等級3」です。
居住環境
住宅の良好な景観やそのほかの住居環境の維持・向上に配慮することに関する基準です。景観計画や地区計画、条例によるまちなみなどの計画の区域内では、調和を図ります。
住戸面積
良好な居住水準を確保するために、一定以上の住戸面積が求められます。戸建て住宅の場合は、7平方メートル以上かつ階段部分を除く1階の床面積が4平方メートル以上あることが必要です。
維持保全計画
住居を長く使用できるように、定期点検や補修などに関する計画を立てます。構造耐力部分、給水・排水の設備、雨水の侵入を防ぐ部分について、認定時から30年以上のメンテナンス計画を立て、計画どおりに実施します。
災害配慮
災害発生の恐れがある地域では、想定されるリスクに応じた対策が必要です。危険度の高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じなければなりません。
長期優良住宅のメリット
長期優良住宅には、税の特別措置が適用されたり、住宅ローンの金利が優遇されたり、さまざまなメリットがあります。長期優良住宅のメリットについて、詳しく紹介します。
税の特別措置が適用される
長期優良住宅では、税の特別措置が適用されます。認定長期優良住宅の場合、2024年から2025年末までに居住を開始するなどの要件を満たすと、控除期間13年、最大409.5万円の住宅ローン減税の控除を受けることができます。
ほかにも、登録免許税や不動産取得税、固定資産税が軽減される特別措置が設けられているため、活用するとよいでしょう。
住宅ローンの金利が優遇される
長期優良住宅の場合、長期固定金利住宅ローン「フラット35」の金利が優遇されます。また、返済期間が50年の「フラット50」の利用も可能です。
地震保険料が割引される
耐震性が確保されている長期優良住宅は、地震保険料が割引されます。割引率は、耐震等級や建築物の種類によって異なります。
長期優良住宅のデメリット・注意点
長期優良住宅には、申請の手間と費用がかかることや建築コストが高くなるなど、デメリットもあります。長期優良住宅を検討する際には、メリットとデメリットの両方について、しっかり理解して判断することが重要です。
申請の手間と費用がかかる
長期優良住宅の認定を受けるためには、長期優良住宅の建築および維持保全に関する計画を作成し、着工前に所管行政庁へ申請する必要があります。数万円~十万円程度の申請手数料やメンテナンスなどの費用がかかります。
建築コストが高くなるケースもある
長期優良住宅の認定基準を満たすために、建築コストが高くなるケースもあります。耐震性を上げるために追加工事したり、柱や梁を増やしたりするなど、費用が増加する可能性があります。
まとめ
この記事では、長期優良住宅の認定基準とメリット・デメリットについてお伝えしました。長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用できるよう、構造や設備に措置が講じられた住まいを指します。認定を受けるためには、長期優良住宅認定制度で定められた基準をクリアすることが必要です。税の特別措置が適用されたり、住宅ローン金利が優遇されたり、メリットがある一方で、建築コストが高くなることも考えられるため、注意しましょう。税の特別措置や住宅ローン金利が優遇される長期優良住宅のマイホームを、検討してみてはいかがでしょうか。